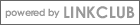Archive for 04 March 2006
04 March
地球環境考慮の経済政策はいつになったら?
今政府・与党の中で竹中総務相・中川政調会長を中心とする「上げ潮派」と、与謝野経済財政担当相・谷垣財務相、それに日銀を加えた「堅実派」との間で、財政再建・金融政策をめぐる対立が続いている。しかしその対立は、せいぜい名目成長率を4%にするか、もう少し低めに見積もるか位の対立でしかない。いずれも「成長」を絶対的与件とする立場である。一方、世界的に「持続可能な経済」を指向すべしという、いわば地球環境の危機的現状に警鐘を鳴らす有力な勢力がある。地球環境が本当に危機的であるなら、当然現実の経済政策はそのことをふまえた上で作成されなければならないのに、この両勢力の交点は全くないように見える。
今経済財政諮問会議で現実の経済政策を論じている人たちの頭には、地球環境の問題などはかけらほども入ってきているように思えない。本来なら環境省というものがあるのだから、この会議の席に環境相も出席して、その議論に大きな方向を与えなければならないのに、環境省はせいぜい他省庁や産業界が反対しないような線で、当たり障りのない政策を出すにすぎない。
中川政調会長は、1月27日、スイスのダボス会議(世界経済フォーラム年次総会)の関連行事として開いた日本主催の夕食会で挨拶し、今夏をめどに名目成長率4〜5%を目標とする自民党の成長戦略をまとめる方針を明らかにした。これを「日本版ライジングタイド(上げ潮)政策」と命名した。
マスコミも例えば日経新聞は、「大国に責任ある行動迫る地球異変」という社説(05年10月19日)を出しながら、その舌の根も乾かないうちに、「経済が低迷した後、新たな成長を目指そうとしなかった先進国はない」「まして日本は人口減少時代が待ち受けている。(中略)よほど思い切った成長戦略を打ち出さない限り、縮み経済のスパイラルに落ちる危険がある」(06年1月16日、岡田直明・論説主幹)と、成長指向一本槍である。
しかし目を地球温暖化というただ一点に絞ってみても、危機は明日のことではなく、今足下で着々と進行している現象である。それを幾つか並べてみよう。
1. 気象庁05.10発表の異常気象レポート
観測データが残る1898年以降の日本の平均気温は、1.06度高くなった。気温の上昇は大都市ほど顕著である。この100年で東京3.0度、名古屋2.7度、福岡2.6度上昇している。CO2排出量が今後も増え続けると、100年後には日本の平均気温は2〜3度上昇する。東京は鹿児島並みの気温となる。
海面水位もこの100年で12cm上昇した。1990年以降では、海面水位は1年当たり約3.8mmの割合で上昇しており、過去100年の上昇率より大きくなっている。2月28日のNHKの報道によれば、南太平洋に浮かぶ島国ツバルは、大潮のこの時期、海水に洗われる土地が増え、スポンジ状の珊瑚礁から成り立っている土地だから、あちこちに海水が噴き出す穴が出現している。海面上昇はこれらの島嶼国にとっては文字通り国の存亡の問題である。オーストラリアやニュージーランドへの国を挙げての移住を真剣に検討している。
植物の開花は早まり、桜の開花は全国平均4.2日早まった。一方カエデの紅葉は、15,6日、イチョウの黄葉は10.8日遅くなった。
2004年は観測史上2番目に高い年平均気温を記録し、東京大手町で真夏日が40日連続、7月20日、39.5度の過去最高気温となるなど、各地で高温記録が更新された。このほか異常多雨、台風上陸10個の新記録も作られた。
気温上昇で懸念されているもう一つの問題は、これまで熱帯病と考えられていたマラリアなどの疾病が、温帯地方にまで広がることである。
2.航空宇宙局(NASA)その他の観測
陸上温度、衛星から測定した海表面温度、船上測定の結果から、NASAおよび世界気象機関(WMO)は、2005年はこれまでで最も暖かい年であったと発表した。北極海の気温が過去50年で4度上昇した。その結果05年夏の北極の氷冠が、過去の平均記録より20%も小さくなった。
世界170人の科学者・専門家の報告書によると、世界の平均気温が今より2度以上も上昇すると、グリーンランドの氷床が融け始め、北大西洋海流の減速・停止、アマゾンのサバンナ化など、「激烈な気候変動」が起きるという予測がなされている。今の世界の経済成長率では、最短で2026年(僅か20年後ですぞ!)には2度を突破するとの予測もなされている。
05年相次いでアメリカを襲った強烈なハリケーンは、メキシコ湾の水温上昇がその発達を促したという説が有力である。
3. 中国科学院青海チベット高原研究所等によるチベット氷河の解凍観測
平均標高が4000mを超える世界の屋根チベット高原は、長江、黄河、怒江、メコン川、インダス川、ガンジス川などの源流である。同高原と周辺の氷河は46298平方キロに及ぶが、この40年間で平均7%縮小した。今後百年でチベット高原の氷河の50~60%が減る可能性がある。
ここには1000を超える面積1平方キロ以上の氷河湖がある。氷河の解凍のため、氷河湖の水位が上がって牧草地が水没し、村ごと3回も引っ越しした例がある。
青海省の黄河源流域の氷河が、00年までの34年間で17%縮小した。その縮小速度は過去300年の10倍である。氷河後退の原因は地球温暖化による季節風の変化によって説明されている。すなわち海面温度の上昇でインド洋などから大陸に吹き付ける湿気を含んだ夏の季節風の期間が長引いて降雨量が増える一方、大陸から海洋に吹き出す冬の季節風が弱まって降雪量が減った。黄河の流量が減り、源流域の地下水の水位が下がって水不足の可能性が高くなっている。
雲南省とチベット自治区との境界に聳える「聖山」梅里雪山から伸びるミヨン氷河も、年に20~30m後退している。この氷河は59~71年の間には800mも前進していた。この付近の平均気温は過去30年で1度上昇し、積雪量が減少して氷河の後退を加速させている。
4. 「Science」の論文
南極大陸西側のアムンゼン海に流れ込む6つの氷河がこの15年間で流れの速度を上げており、しかもそのペースが最近になってさらに速まっているとしている。その中でも最も速いパインアイランド氷河は、1日約5.5メートルのペースで流れており、地球上で最も動きが速い氷河のうちに数えられるまでになっている。この速度は、1970年代と比べると25%も上がっている。
アイスレーダーを搭載した調査用航空機で調べた結果、アムンゼン海に流れ込む6つの氷河は、これまで考えられていたよりも平均で約390メートル厚く、海に流れ込んでいる氷の量も非常に多かったことが判明した。リグノット博士によると、6つの氷河が完全に海に落ちて溶けた場合、地球全体の海面が90センチ以上上昇するという。
ちなみにもし1m海面が上昇すれば、日本の人口の3%、410万人が住む家を失う。
5.「Nature」誌の2004年1月8日号
温室効果ガスの排出量を大幅に削減しなければ、地球上に存在する全動植物種の4分の1が2050年までに絶滅する。
このほか地球温暖化を示すデータは枚挙にいとまがない。そのどれも今すぐに対策がとられなければ手遅れになることを示している。しかし温暖化を防ぐ政策は遅々として進んでいない。1997年に採択され、05年2月16日に発効した京都議定書には、温暖化ガス排出量世界一のアメリカ、2位の中国、5位のインドが含まれていない。
特に世界排出量の4分の1を占めるアメリカが、経済活動への悪影響を理由に京都議定書から離脱したのは、全く利己的な行動であって、大いに非難されるべきである。アメリカがこういう態度をとり続ける限り、中国、インドなどの途上国扱いの国々が、協力するはずがない。そのアメリカが猛烈ハリケーンで大きな被害を出したのは、まさに「身から出た錆」であった。「利己」のつもりが「損己」になっている。
さすがにアメリカでも、ニューヨーク州など北東部7州、カリフォルニアなど西部3州などは、独自のCO2削減策や新規制を打ち出している。この動きには、来るべき大統領選への野心という不純な動機も含むようであるが、州レベルから中央政府に圧力をかけ、少しでも温暖化防止に役立つのであれば歓迎すべきことであろう。またブッシュ政権は、全米科学アカデミーからもたしなめられ、COP11(第11回国連気象変動枠組み条約締結国会議)も、京都議定書反対の取り消しを要求した。
振り返って我が日本の実情はとなると、こちらも決して威張れる話ではない。京都議定書で日本は、2008〜2012年の間の平均で、温暖化ガス排出量を90年の水準から6%減らす約束をしている。ところが減らすどころか、03年で8%増えている。とくに民生部門、運輸部門などの増加が大きい。この6年以内に14%減らすのは至難の業である。政府は約1億トン分の削減に相当する排出権を購入する腹づもりである。
しかし排出権の価格は、今後数年間で2〜4倍に高騰すると言われている。05年の水準のままなら、1億トンを買うのに約700億円かかる計算だが、予想される価格高騰があれば、2000億円以上かかることになる。早くから排出権の手当をしてきたヨーロッパ諸国は、すでに安く購入したと言われている。
日本で唯一排出量を僅かながらマイナスにできたのは産業部門である。その努力の甲斐あって、日本のエネルギー使用効率は世界主要国のトップである。GDP1単位当たりのエネルギー消費量は、ドイツが日本の1.4倍、米国が2.8倍、中国が9倍、ロシアに至っては18倍である。これら効率の悪い国々、特に中国は、日本が技術移転をして排出権を獲得する絶好の場である。こういう経済交流、環境協力こそ、互いにWin –Winの関係を結べる。それも小泉の靖国参拝と言う愚行によって、話し合いさえできない状態が続いている。
ローマクラブによる「成長の限界」が出されてからすでに40年、この後にも人類は多大の資源を食いつぶし、地球環境を汚染し続けてきた。そしてその行動規範は、今後も中国やインドのように急成長を遂げつつある人口大国によって、もっと過激な形で引き継がれている。中国では今や車ブームである。このモータリゼーションがどういう地球をもたらすか、誰でも容易に想像することができるだろう。
1987年の国連後援のブルントラント委員会報告書で用いられて以来、「持続可能な発展」という考えが出てきたが、では実際に何をしたら「持続可能」になるのかの答えが容易には出てこない。96年に書かれ最近日本語訳も出たHerman E. Dalyの「持続可能な発展の経済学」(Beyond Growth―The economics of Sustainable Development)によると、「量的拡大(成長)という経済規範を、質的改善(発展)という経済規範に置き換える」ことが必要になる。
このような発想の転換は「大部分の経済組織や政治組織の抵抗」を受ける。いま日本の政策を決めている集団は、小泉、竹中を含め、その発想からしてまさに「抵抗勢力」である。「持続可能な経済システム」が、未来の人類には福音をもたらすとしても、現在生活している人たちには生活レベルの低下をもたらすのできわめて不人気である。選挙で政権が決まる民主主義国では、「持続可能な経済」を主張する政党は選挙で勝てないだろう。政策の受益世代と、政策の決定世代とが異なっていることがこの問題の難しさである。その点で財政赤字解消問題に性格が似ている。
こうして今のままでは、発想の転換なしにずるずると破滅的状態に人類を導く可能性が高い。金子勝・慶大教授の言葉を借りれば「地球の悲鳴を聞こうとしない者たちは、遠くない未来に人々の悲鳴を聞くことになる」(朝日新聞、05.10.26 夕刊「論壇時評」)。京都議定書から離脱したブッシュ政権が、ニューオーリンズの人たちの悲鳴を聞いたのは、その悲鳴の走りであったろう。
少なくとも、目下の政治が金科玉条としている「グローバリゼーション」「自由貿易」「メガコンペティション」「資本原理主義」「成長することはよいことだ」などの概念が、「持続可能な経済」と両立しにくいことは間違いない。
人類はいつになったら「地球の悲鳴を聞き、『清貧』に甘んじる政策」を受け入れるようになるだろうか? ヒトはそこまで賢いのかと問われれば、筆者は楽観的にはなれない。
(2006.3.4)
21:21:23 |
archivelago |
|
TrackBacks